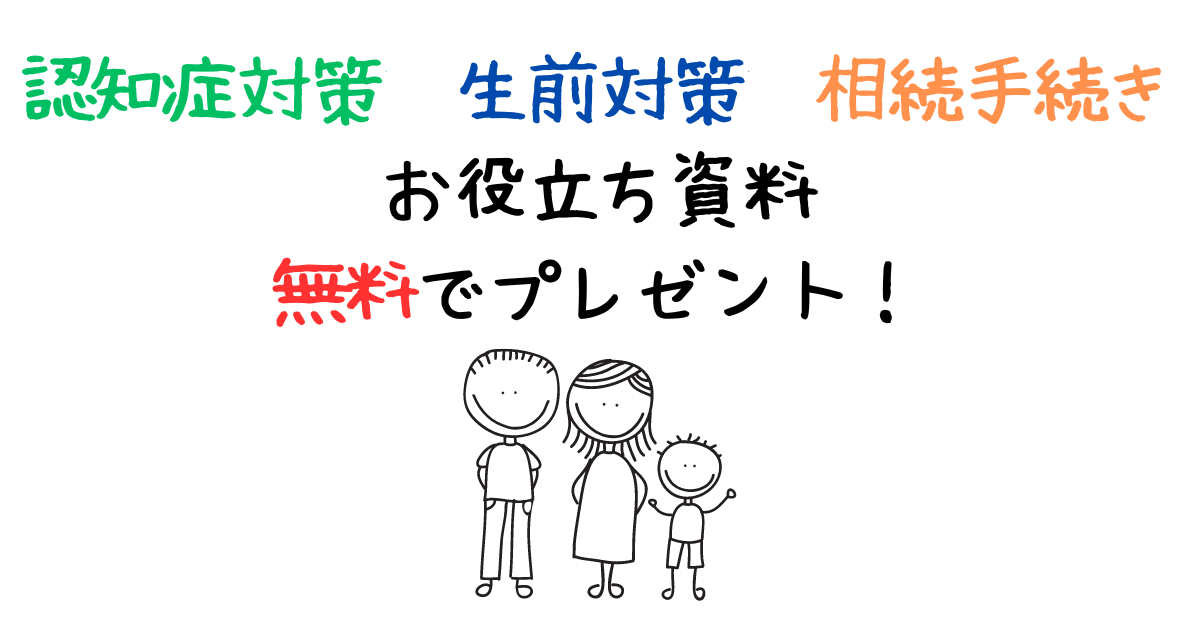以前の記事で任意後見契約について書きました。
今日は、任意後見契約に付随する契約の死後事務委任契約の費用についての解説です。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、委任者が生存している間に代理権を付与して自分の死後の葬儀や埋葬に関する事務について委託する委任契約の一種です。
死後における一定の事柄に限定した契約であり、委任者が死亡した後に効力が生じ、実際に契約に基づいて手続き等を行うときには契約の意図や内容を確定する当事者の一方が存在しない少し特殊な契約です。
また、委任者の相続人からの解除権放棄の特約がある委任契約です。
※解除権の放棄とは、委任者(死後事務委任を実際に結んだ人)の相続人が死後事務委任契約を相続権に基づいて放棄(契約を放棄)しようとしても死後事務委任契約の特約により、放棄(契約の放棄)をすることが出来ないような契約設計になっています。
契約の内容は具体的に、施設や病院で死亡した場合の未払いの施設利用料、入院費の支払い、遺体の引き取り、葬儀(そもそも葬儀をするのか?)、火葬、納骨、永代供養をするのか?、居住していた施設の片づけ、遺品整理などの事務手続き全般をすることです。
遺言とは別に、信頼できる人に委任し、委任を受けた人(受任者)が契約上の義務として履行することになります。
死後事務委任契約の費用

・契約書作成費用
8万円(弊所の場合)
死後事務委任契約は、契約内容がある程度確定していれば、契約書の証明力を担保し、相続発生後の手続きを円滑にするためにも、公正証書で作成した方が良いでしょう。公証役場手数料は1~2万円程度かかります。
・死亡後の事務手続き費用
70万円(上限を70万円として、行う事務手続きの種類と煩雑さに応じて変わります)*弊所の場合
70万円と聞くとギョッとされる方もいるかもしれませんが、死後事務委任契約で行う手続きには、お寺さんへの連絡、納骨の手続きは誰がするのか、お墓の管理はご本人の死亡後できる人がいるのか、いない場合には受任者がするのか、遺品整理は必要なのかなどなど手続きは、多岐になります。
これらの手続きの責任を考えると、決して高い金額とは言えません。
死後事務委任契約の費用相場は?
死後事務委任契約を業務として提供している事業者は以下のようなところがあります。
士業(司法書士、弁護士、行政書士)
NPOなどの法人、民間企業(福祉系施設などを運営する会社)
これら事業所に応じて、費用相場は異なります。
Web上で公開されている情報を基に各分野ごとの費用相場は以下の通りです。
上記でも説明した通り、死後事務委任契約では、契約書作成時にかかる費用と実際に相続が発生した時に必要になる費用があります。
士業(司法書士、弁護士、行政書士)の費用相場
・契約書作成時 数万円~20万円程度
・死後事務手続き時 30万円~100万円程度
NPOなどの法人、民間企業(福祉系施設などを運営する会社)の費用相場
・契約書作成時 数万円~10万円程度
・死後事務手続き時 30万円~150万円程度
※預託金という形で、数十万円の費用を預ける必要がある団体も多くあります
司法書士太田合同事務所からのアドバイス

死後事務委任契約の費用について解説しました。
遺言書や後見制度に比べると、認知度の低い死後事務委任契約ですが、特におひとりさまの方や子供さんのいないご夫婦などは契約を結ぶメリットが大きいと思います。
死後事務委任契約の特徴として、我々のような士業だけでなく、法人や民間企業なども参入しているサービスですので、サービスを利用する時には、信頼のおける団体なのか、実績はあるのかなどしっかりとご自分でリサーチされることをお勧めします。
特に死後の事務手続きでは、相続人が解除できないような規定になっていることもありますので、費用が思った以上にかかり、解除したいけどできないというような状態にならないように、注意が必要です。
死後事務委任契約は、任意後見契約とセットでされる契約です。
任意後見のことについても、「認知症対策そうだん窓口」で詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。
厚生労働省の任意後見制度についてのホームページはこちらです。