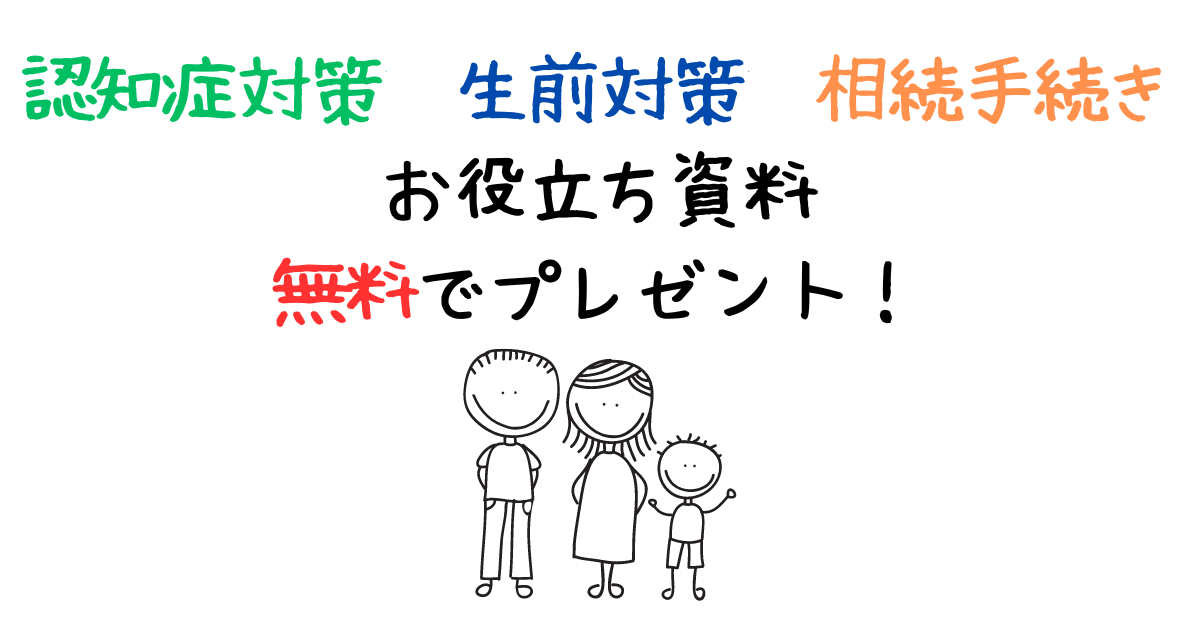以前の記事で任意後見人の権限と法定後見人の権限についての違いについて、書きました。
今日は任意後見制度のデメリットについての話です。
目次
任意後見制度のデメリット

既に認知症だと契約ができない
任意後見契約は、ご本人(認知症を心配されている人)と後見人になる予定の方(親族、友人知人、専門職)との契約です。
ご本人が認知症になってしまうと、そもそも契約できる判断力がありませんので、契約できません。
これは任意後見制度のメリットの裏返しとも言えますが、法定後見と違い、認知症になる前から契約(後見の予約)が出来る代わりに、契約時に本人に正常な判断力が求められるわけです。
法律行為をする際に必要とされる「意思能力」については、様々な考え方があります。
意思能力について、別の記事で解説していますので、そちらをご覧ください。
任意後見人が死亡したり、解任されると法定後見に移行する
任意後見人に不正行為があると、任意後見監督人や本人、その親族などが裁判所に解任の請求をすることで、解任されます。
その後は、新たに任意後見人は選任されませんので、代わりに法定後見に移行します。
法定後見になれば、専門職などが後見人になりますが、ご本人にとっては見ず知らずの人が後見人になる確率が高くなってしまいます。
決して、法定後見を否定しているわけではありませんが、認知症になる前からご本人と信頼関係を築いて、任意後見契約をした意味がなくなってしまいますし、なによりご本人の意思の尊重にはなりません。
またご本人や後見人が死亡した場合にも契約が終了してしまいますが、これは契約内容によって、回避することができます。
ご本人の死亡はどうしようもありませんが、受任者(後見人になる予定の人)側の死亡は受任者を複数名用意して、複数の任意後見契約を結んだり、法人が受任者(法人は解散しない限り、担当者が変わっても無くなりません)になれば回避できます。
契約書はすぐに作れない
任意後見契約は、認知症になった際の財産管理や法律行為の代理についての契約です。
いざご本人が認知症になってからでは、ご本人の意思を確認することはできませんので、細かく契約内容を決めておく必要があります。
そうなるとご本人と何度も面談をし、ご本人の希望を聞き出して、契約内容を作っていくことになります。
任意後見契約書を作りましょう!と言ってもすぐに作るのは難しいのかなと思います。
実務上、しっかりとご本人の希望を聞いているのか非常に疑わしい、曖昧な状況で契約書を作成しているような、団体や組織がいることを風の噂で聞いたりもするのですが、これは非常に危険ではないかと思っています・・・。
任意後見契約書は公正証書に作成しなければいけない
任意後見契約に関する法律では以下のような規定があります。
(任意後見契約の方式)
第3条
任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
任意後見契約は、契約者同士が個別の事情に応じて契約内容を作成することができる(オーダーメイドの契約内容)というメリットがあります。
ただし、当事者のみで決めてしまうと(特に契約当事者が一般の方同士のケース)当事者が理解できない内容で任意後見契約を締結してしまい、任意後見契約が発効した際は、契約当事者は、その契約内容に拘束されることになってしまいます。
そこで、契約書自体を公正証書で作成することを法律で義務化することで、公証人による契約内容のチェックや契約当事者の判断能力・意思確認を行い、契約内容の適切であることが確認されることになっています。
司法書士太田合同事務所からのアドバイス

任意後見契約は、法定後見とは異なる制度ではありますが、立派な後見制度の一部です。
法定後見と異なるメリットもたくさんありますので、任意後見契約を結ぶことがご自身に合った適切なものであれば、非常に有用な制度だと思います。
この記事では、デメリットについて書きましたが、当然たくさんのメリットもあります。
特にオーダーメイド型の契約内容が可能で、ご本人の希望をそのまま契約書に落とし込めるのは任意後見契約の大きなメリットだと思います。
任意後見契約について興味関心のある方は、恐らく生前対策について検討をされていて、この記事を見ているという人も多いのではないでしょうか?
生前対策は、任意後見契約以外にも家族信託、遺言、生前贈与、死後事務委任、財産管理など多種多様です。
重要なのは、ご自身に合った適切な生前対策の制度を利用することです。
法律専門職を利用して自分自身、ご家族の生前対策について考えてみてください。
厚生労働省の任意後見制度についてのホームページはこちらです。
任意後見のことについて、さらに詳しく知りたい方は、「認知症対策そうだん窓口」で任意後見のことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。