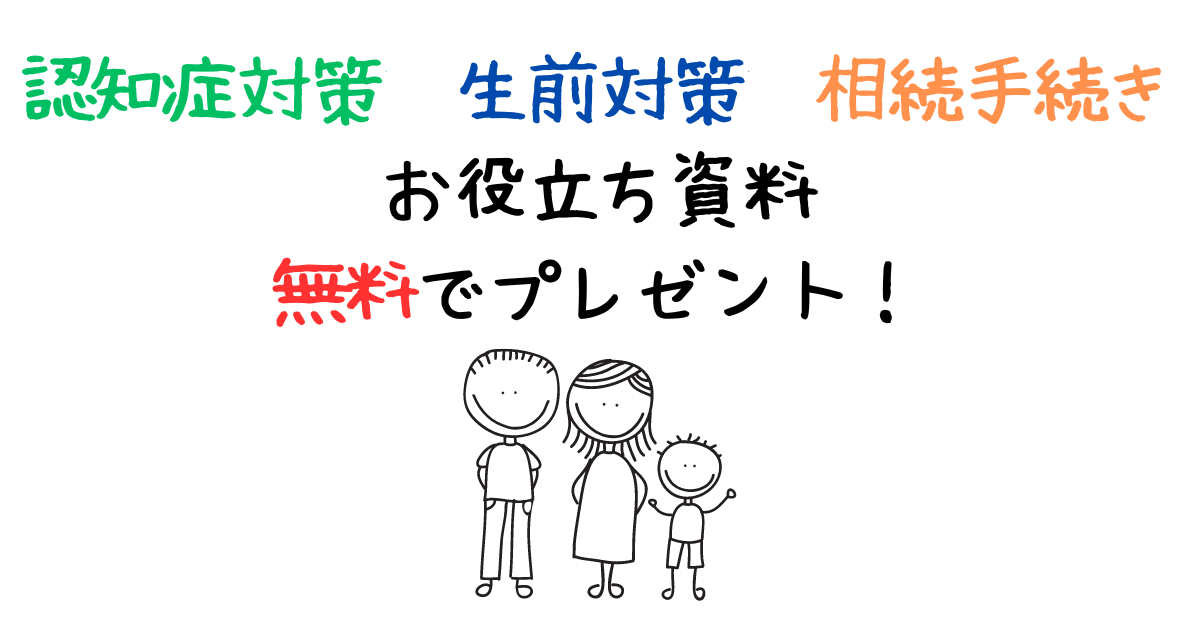遺言書には主に、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
これらは有効要件を満たしていないと、そもそも法律的に使用できません。
そうなると、様々な相続手続きで遺言内容通りに、手続きが進められなくなる恐れが出てきますので、注意が必要です。
今回は、遺言書がどんな場合に無効になってしまうのかを解説していきます。
遺言が無効になる例
・自筆証書遺言で方式が具備されていない
例 全文、日付、氏名が自書でない・押印がない など
上記はあくまでも、法律上の規定ですが、仮に法律上の規定を満たしていても、自筆証書遺言で注意しなければいけないこととして、預金解約などで金融機関に遺言書を提出する場合には、金融機関指定の用紙に相続人全員の実印押印がなければ預金の払出しができないというようなケースもあるようなので、自筆証書で相続手続きする場合は注意が必要です。
・遺言能力を満たしていない
遺言能力は、遺言の内容、遺言者の年齢、心身健康状態、遺言時及びその前後の言動、遺言時から死亡時までの時間的間隔など総合的に判断されます。
意思能力に関することは別の記事で解説していますので、そちらをご覧ください。
・遺言内容が不確定
例えば、遺産をあげる人(受遺者)を第三者に一任するという内容の遺言は無効、という裁判所の過去の事例があります。
専門職が関与している遺言書については、疑義が出ないような内容にしているとは思いますが、一般の方がバイマイセルフで作成する遺言書の場合、読み手に誤解が生じてしまうような、微妙なニュアンスの表現は避けて作成するように注意しましょう。
相続人や受遺者に誤解が生じないように、遺言書の内容は、明確に遺言者の意思表示がされる必要があります。
・公序良俗に反する内容
例えば、愛人に相続財産を渡す内容の遺言の場合に無効になる可能性があります。
過去の裁判例として、以下のようなものがあります。
社会福祉法人が経営する養護盲老人ホームに入所していた者がした、同法人に葬儀費用等を除いた財産全部を包括遺贈する旨の公正証書遺言が錯誤により無効とされた事例。
(さいたま地熊谷支判平27.3.23判時2284号87頁)
ただし、注意してほしいのは、遺産の全部を特定の相続人のみに遺贈したからといって、それがためだけの理由で、直ちに当該遺言が公序良俗に反し無効であるとはいえないという裁判例もあります。
(最判昭37.5.29家月14巻10号111頁)
・法定遺言事項に該当しない遺言
遺言は、法律で定められた事項に限り、遺言の内容にすることができます。
そして、それ以外の事項は遺言の内容になっていても、法律上の効力はありません。
法定遺言事項は例えば、遺贈、信託、遺産分割の禁止などです。
司法書士太田合同事務所からのアドバイス

以上のように遺言書が無効になってしまうケースは以外にも多くあります。
せっかく費用と手間(特に公正証書遺言の場合)をかけて遺言書を作ったのにいざ相続手続きをする際に無効事項があって手続きに利用できなかった・・・なんてことにならないように遺言書作成には十分注意しましょう。
遺言書と聞くとイメージとしては「誰々に相続させる」というような簡単なものをイメージされる方も多いのではないでしょうか?
実際には、生前対策の一つの選択肢になるものですので、様々な事情(遺言者の希望、相続人、遺言者と相続人との関係性、資産の額や種類など)を考慮しながら、遺言書の内容や作成するタイミングなどを決めていくのがいいかと思います。
特に相続資産が高額になりやすい方は、専門職に遺言書の内容をチェックしてもらったほうが無難かと思います。
遺言書のことについて、さらに詳しく知りたい方は、「遺言書そうだん窓口」で遺言書のことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。