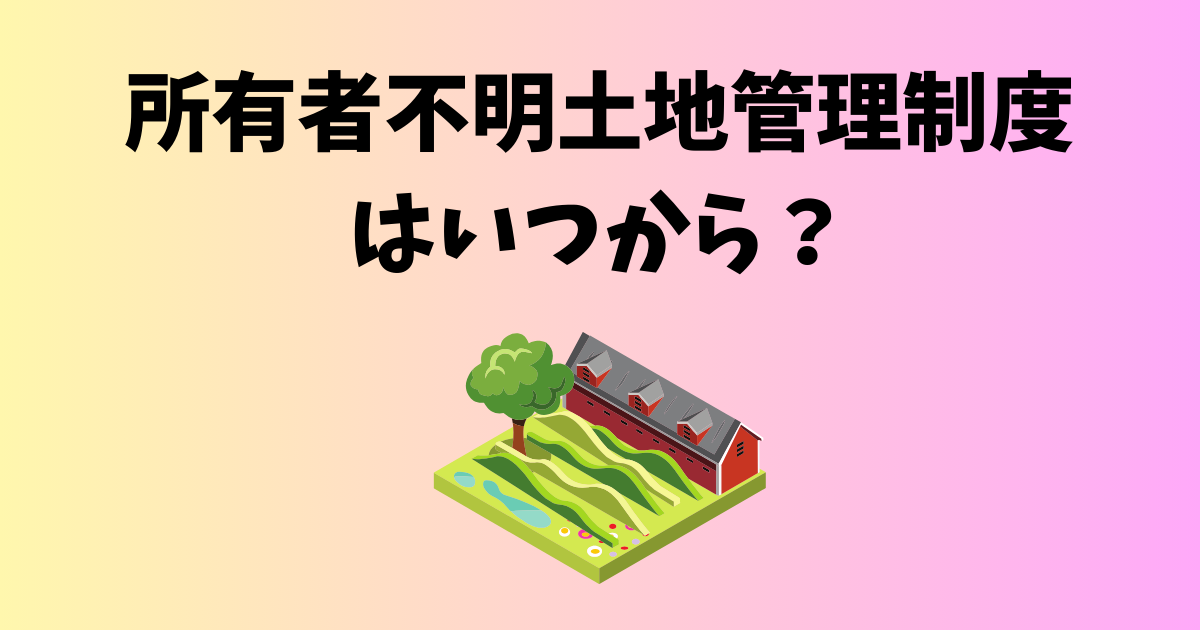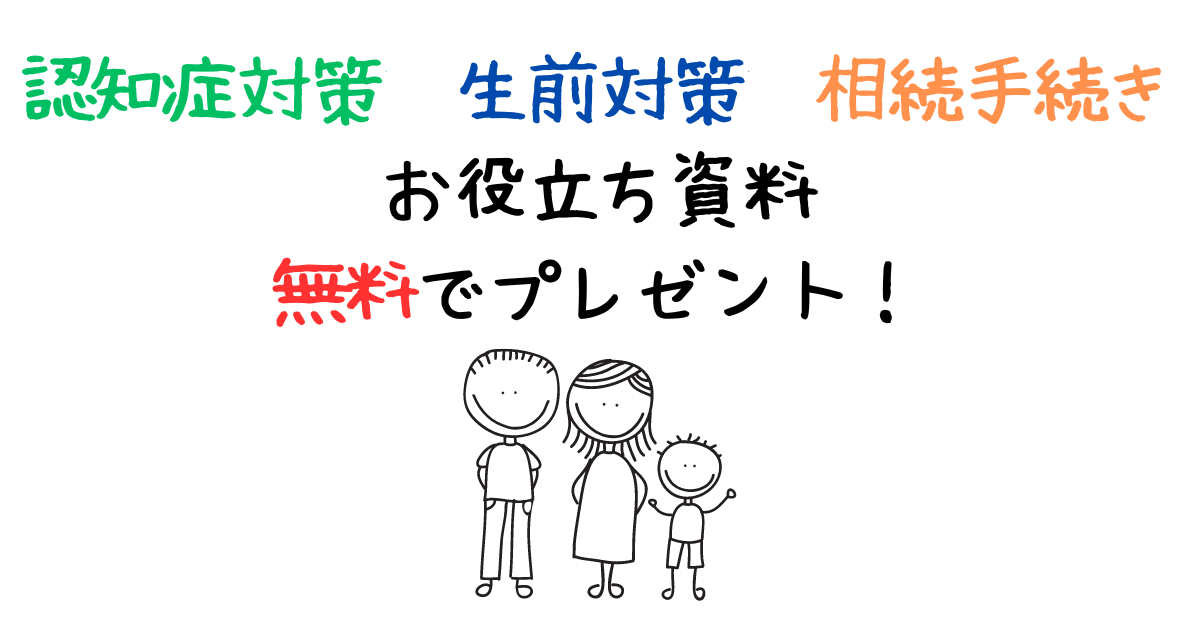太田合同事務所では、豊橋・湖西・浜松・豊川で相続手続きでお困りの方に向けて、相続手続き相談、手続き代行の専門サイト「相続そうだん窓口」を運営しております。
相続登記、遺産分割協議書の作成、戸籍収集、銀行口座手続き、保険金請求など相続手続きをサポートするサービスをご提供しています。
お気軽にお問い合わせください。

目次
この制度はいつから?

所有者不明土地管理制度ですが、令和5年4月1日からスタートしています。
この制度は、国が所有者不明土地の発生防止と利用促進のために関係法令を見直すという観点からスタートした制度です。
相続登記の義務化や住所変更登記の義務化、相続土地国庫帰属制度なども所有者不明土地の発生防止という目的のために創設された法律、制度です。
(注)相続登記義務化は令和6年4月1日、住所変更登記義務化は令和8年4月1日、相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日からスタートです
今後高齢化社会が見込まれる中で、死亡者数の増加とともに、所有者不明土地が増加して問題が深刻化することを危惧した国が法律を改正したというのが、これらの制度ができた背景です。
所有者不明土地(建物)管理制度とは

所有者不明土地管理制度とは、以下の法律に基づいて規定された制度です。
(民法264条の2)
裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人(第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明土地管理命令」という。)をすることができる。
(民法264条の8)
裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人(第四項に規定する所有者不明建物管理人をいう。以下この条において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「所有者不明建物管理命令」という。)をすることができる。
今までの民法では、不在者(居所が知れない人)の財産や相続資産で相続人がいない場合など、それぞれのケースに応じて法律が規定されていたのですが、これだと、財産の管理が非効率になりがちで、利用者にとっても負担が大きいものでした。
また所有者を全く特定できない土地・建物については、既存の法律(財産管理制度)を利用することができないというデメリットがありました。
新しい法律では、特定の土地・建物のみに特化して管理を行う、所有者不明土地管理制度及び所有者不明建物管理制度を創設することで、財産管理の効率化と利用者の負担の軽減を図っています。
また新しい制度では、所有者が特定できないケースについても対応が可能になりました。
管理対象財産
上記で記載した通り、裁判所は利害関係人の申し立てによって、所有者不明土地(建物)の管理命令が出来る訳ですが、この管理命令はどの財産にまで及ぶのでしょうか?
新しい法律では、管理命令の効力は、所有者不明土地(建物)のほか、土地(建物)にある所有者の動産、管理人が得た金銭等の財産(売却代金等)、建物の場合はその敷地利用権(借地権等)にも及ぶが、その他の財産には及ばないとしています。
ちなみに、所有者不明土地の上に所有者不明建物が建っている場合、双方を管理対象財産にするためには、各別に申し立ての手続きをする必要があり、土地と建物の所有者が別の場合には、管理者を同一に出来るかどうかは、慎重に判断されるとのことです。
申立て権者
所有者不明土地(建物)管理制度の申立てが出来る人(申立て権者)は、利害関係人となっています。
具体的に利害関係人とは以下のような人です。
●公共事業の実施者など不動産の利用・取得を希望する者
●共有地における不明共有者以外の共有者
(注)地方公共団体の長等にも所有者不明土地管理命令・所有者不明建物管理命令の申立権の特例があります(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法42条2項)
要件
この制度の申し立て要件は以下の通りです。
① 調査を尽くしても所有者又はその所在を知ることができないこと
所有者の調査方法は以下のようになります。
《登記名義人が自然人である場合》
登記簿、住民票上の住所、戸籍等を調査
《登記名義人が法人である場合》
法人登記簿上の主たる事務所の存否のほか、代表者の法人登記簿上・住民票上の住所等を調査
《所有者が法人でない社団である場合》
代表者及び構成員の住民票上の住所等を調査。
② 管理状況等に照らし管理人による管理の必要性があること
(注)事案に応じて現地調査が求められることもある。
(注)処分の有無について法的判断が必要となるケース(売却代金額の相当性の判断、数人の者の共有持分を対象として管理命令が発せられ、誠実公平義務の履行が問題となるケースなど)では弁護士・司法書士を境界の確認等が必要となるケースでは土地家屋調査士を管理人として選任することがある。
(注) 区分所有建物については、所有者不明建物管理制度は適用されない(区分所有法6条4項)
管理人の権利義務
管理人が選任された場合に、管理人が権限として出来ることですが、対象財産の管理処分権は管理人に移り、管理人は、保存・利用・改良行為を行うほか、裁判所の許可を得て、対象財産の処分(売却、建物の取壊しなど)をすることも可能です。
(民法264条の3の2項、264条の8の5項)
管理人は、所有者不明土地等から、裁判所が定める額の費用の前払・報酬を受けることになります。
ちなみに費用・報酬は所有者負担となります。 (民法264条の7 1・2)
手続きの流れ
申立先は、不動産所在地の管轄裁判所です。
利害関係人が申し立てを行い、予納金(管理費)を納入する必要があります。
事案に応じて、弁護士・司法書士・土地家屋調査士が管理人として選任されます。
司法書士太田合同事務所からのアドバイス

所有者不明土地(建物)管理制度は既に施行されている制度です。
要件事項は比較的少ないため、ハードルが低そうに感じる方も中にはいるかもしれませんが、要件②については明確な基準とは言えないため、裁判所の裁量が強いのかなと思います。
また管理人として、弁護士等の第三者が介入する可能性や予納金(裁判所に支払う費用)もあります。
利用する際は、そのあたりのことも考慮したうえで、手続きをしましょう。
この制度を利用するには、裁判所への書類等の提出が必要になりますので、手続きの前に司法書士などの法律専門職に相談するようにしましょう。
太田合同事務所では、豊橋・湖西・浜松・豊川で相続手続きでお困りの方に向けて、相続手続き相談、手続き代行の専門サイト「相続そうだん窓口」を運営しております。
相続登記、遺産分割協議書の作成、戸籍収集、銀行口座手続き、保険金請求など相続手続きをサポートするサービスをご提供しています。
お気軽にお問い合わせください。