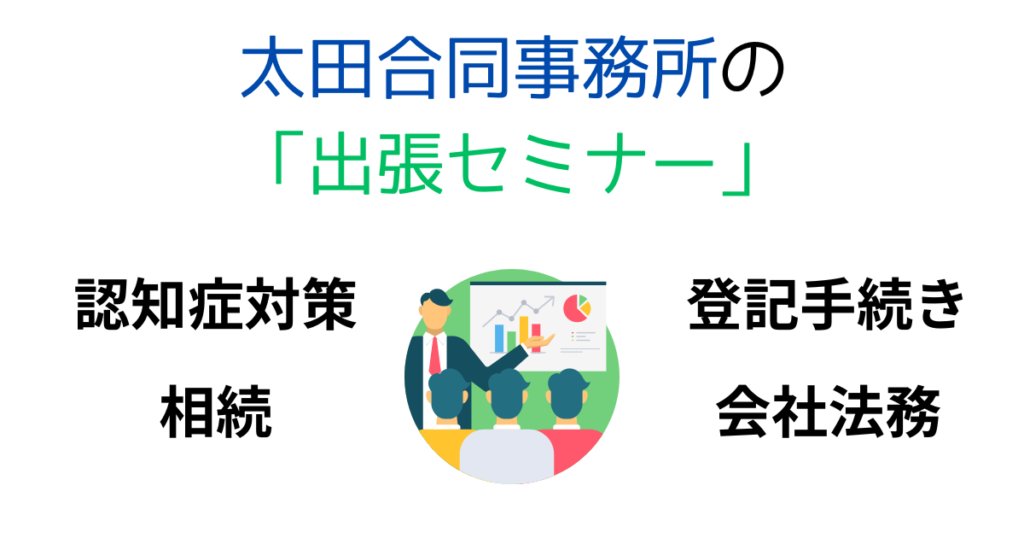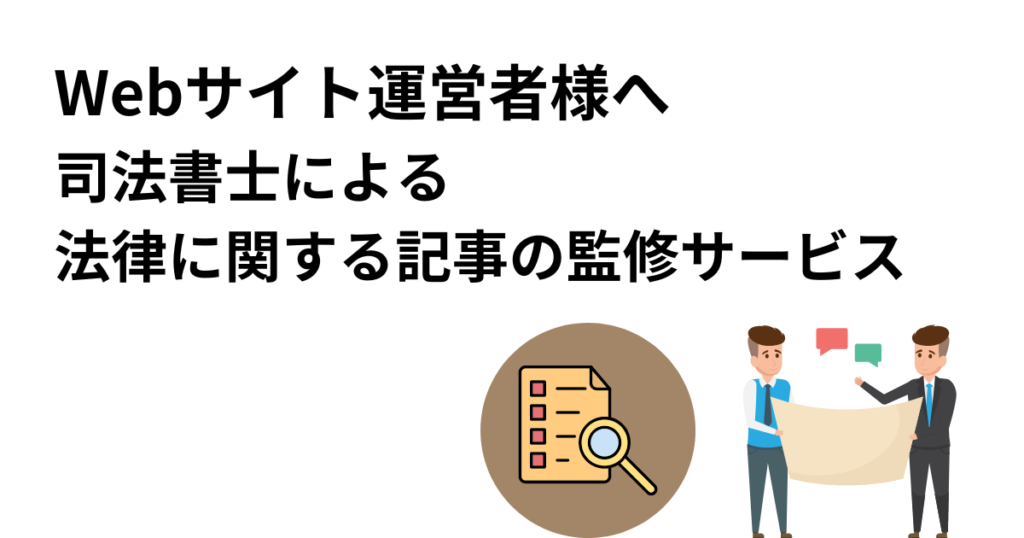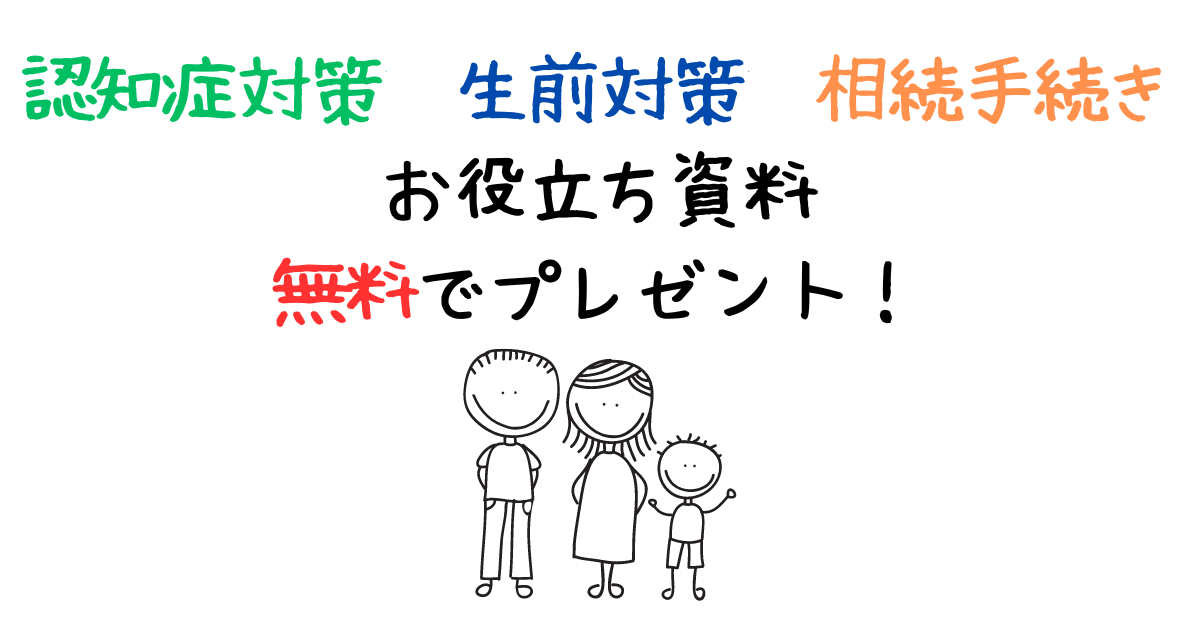サービス案内
太田合同事務所では、法手続きに関するセミナーや法律に関する記事監修を行っております。
セミナーは、NPO法人、葬儀会社、不動産会社、市の社会福祉協議会などでの実績があります。
ご興味のある会社、団体のご担当者様はお気軽にお問い合わせください。
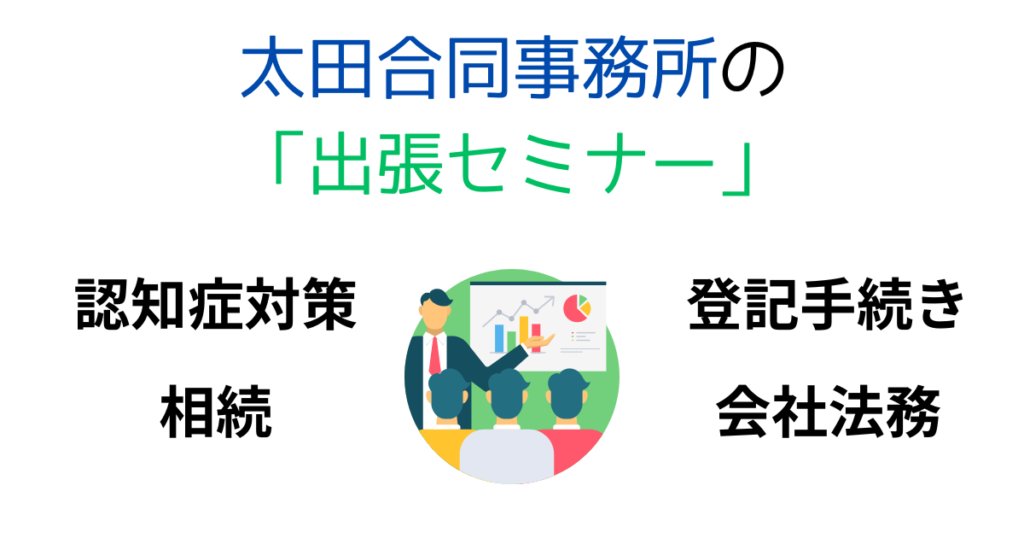
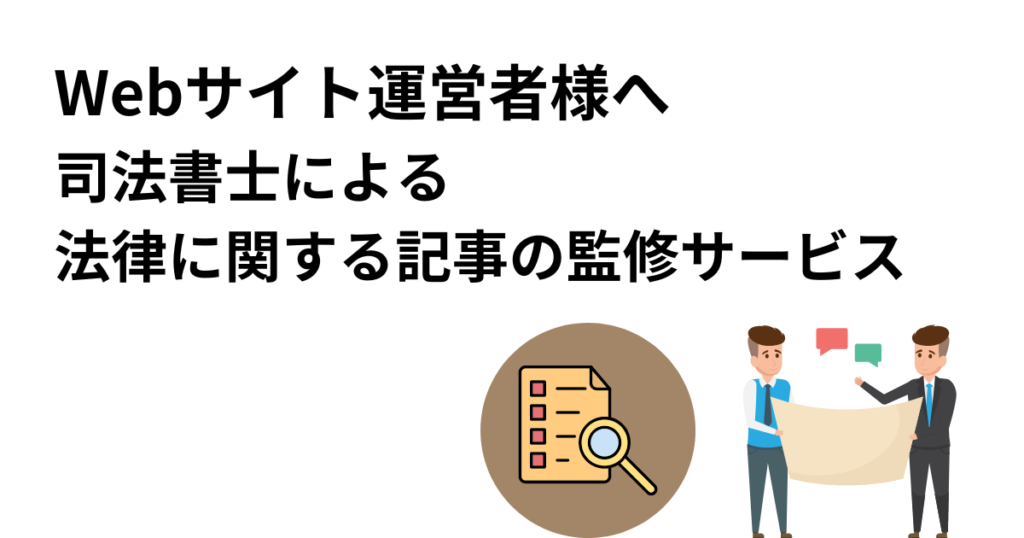
民法の成人年齢を20歳から18歳に引き下げることなどを内容とする民法の一部改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。
法務省は『成人年齢の見直しは、その積極的な社会参加を促し、社会を活力あるものにする意義を有するものと考えられます。』と言っています。
法務省ホームページはこちら
今日は、成人年齢の引き下げによるメリット、デメリットについてです。
なんで成人年齢が変わるの?
民法改正され、2022年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に変わります。
これに伴い2022年4月1日に18歳、19歳の人は2022年4月1日に新成人となります。
成人年齢が引き下げられる理由について、政府は『選挙権年齢を18歳と定めて、若者にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策を進めてきたことや、市民生活の基本法である民法でも、18歳以上を大人として扱うのが適当ではないかという議論がなされたこと』などをあげています。
また、世界的にも成人年齢を18歳とするのが主流となっていることにも触れています。
何が変わるの?メリット、デメリットは?
成人年齢引き下げのメリット、デメリットを考える上で、18歳になると何ができるようになったのか?そして今までと変わらない部分は何か?を確認する必要があります。
18歳で出来るようになったこと
・親の同意がなくても契約ができるようになる
例 携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードを作る、部屋の賃貸借契約など
・結婚年齢が男女18歳になった(今までは女性の結婚年齢は16歳)
・10年有効のパスポートを取得する
・性同一性障害の方が性別の取り扱いの変更審判を受けられる
これまでと変わらないこと
・飲酒、喫煙をする
・競馬、競輪、オートレースなどの投票券を買う
・養子を迎える
さて、これらのことを踏まえて、成人年齢引き下げのメリットとデメリットは何でしょう?
まずメリットとして考えられるのは、法律契約がより若い年齢で結べるようになったことから、より若い年齢で親の介入なしに様々なことが(売買契約、賃貸借契約など)自由に出来るようになったことではないでしょうか。
もちろんこれは、『正しい判断が出来れば』という前提条件がつきます。
裏返しにもなりますが、より若い年齢で法律的リスクを負うようになったとも言えますのでそれはデメリットでしょう。
もう一つ、大きな変化が女性の結婚年齢が18歳になったことです。
結婚年齢が16歳から18歳になることは、メリットととらえるかデメリットととらえるかは、人によると思いますが、私はメリットではないかと考えます。
高校卒業の年齢まで結婚を待つというのは、若い方の冷静な判断を促すうえでも重要な気がするからです。
サービス案内
太田合同事務所では、法手続きに関するセミナーや法律に関する記事監修を行っております。
セミナーは、過去にNPO法人、葬儀会社、不動産会社、市の社会福祉協議会などでの実績があります。
ご興味のある会社、団体のご担当者様はお気軽にお問い合わせください。