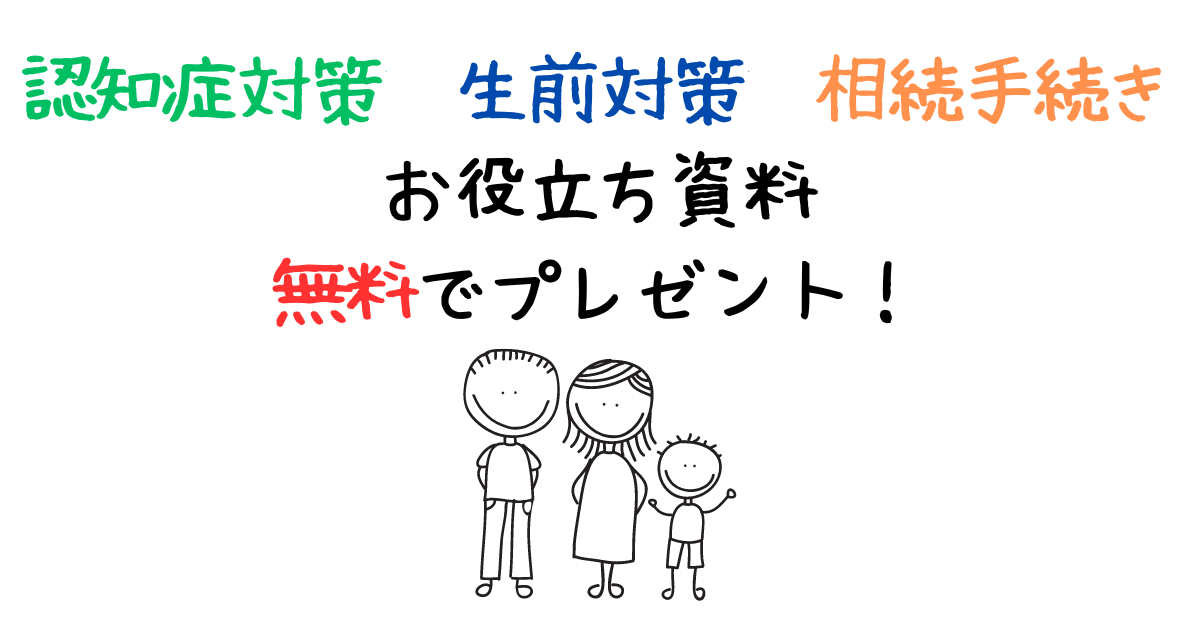今日は、後見人手続きをするための必要書類についてです。
後見人制度を利用するためには、家庭裁判所への申し立てが必要になります。
後見業務を行う上で、最も大変なのは裁判所に提出する申立ての書類を作成したり、収集したりする作業です。
申立ての際に必要な書類について、解説していきます。
目次
後見申し立ての必要書類
申立書
申立人の住所氏名やご本人の住所氏名、申し立ての理由や実際にどういった保護が必要なのか?(例えば、預貯金の管理、不動産の管理など)、また後見人候補者がいる場合には、候補者の氏名、住所などを記載します。
後見申立ては、時間的猶予が無いようなこともあります。そう言ったときは、資料作成に時間をかけるよりも、本人に早く後見人を付ける必要がある場合も多いと思います。
財産目録などは分かる範囲で記載し、分からない部分は「不明」と記載して申立てをした方がよい場合もあるでしょう。
申立て書類の雛型は、ホームページからダウンロードできる家庭裁判所が多いです。
ご本人の戸籍謄本、住所票等(発行から3ヶ月以内のもの)
申立人がご本人の4親等内親族の場合には、それを証する戸籍謄本が必要です
後見人候補者の住民票等
法人が候補者の場合には、登記事項証明書
ご本人の診断書(発行から3ヶ月以内のもの)
平成31年4月1日から診断書が新しい様式になっています。
作成を依頼する医師は、精神科医に限らないため、ご本人のことをよく知るかかりつけ医がいいでしょう。(かかりつけ医でなくても問題ありません)
後見、保佐、補助の申立ての際の選択は、原則的に、診断書の中で医師がチェックした「後見」「保佐」「補助」に従って選択することが多いますが、必ずしも診断書の結果にとらわれず申立てすることを考えることも大事かと思います。
私の知り合いの心療内科の先生で、後見申立ての類型選択について、医師の診断書によって判断して、責任を委ねられるのは荷が重い・・・と仰っていました。
その先生にもよるかとは思いますが、医師は医学的な見地から診断書を出しているかと思いますので、ご本人のことをよく知るご家族や福祉関係者、又はご本人の意思というのも十分配慮すべきかとは思います。
ご本人の情報シート
ご本人の状況をよく把握されている、福祉関係者が作成した書類です。
ご本人の介護区分や障害の等級、認知機能、日常生活の行動障害、意思決定、金銭の管理状況などを記載します。
ご本人の健康状態を関する資料
介護保険認定書、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳の写しなど
ご本人が成年被後見人に登記されていないことを証する書面
(発行から3ヶ月以内のもの)
ご本人がすでに、法定後見制度や任意後見制度を利用していないかを確認するためのものです。
ご本人の財産に関する資料
預金通帳の写しや有価証券の残高証明書、不動産の登記事項証明書など
ご本人の収支に関する資料
収入に関する資料は、年金額の決定通知書、給与明細、確定申告書など
支出に関する資料は、施設利用料、入院費、納税証明書など
親族関係図、親族の意見書
推定相続人の確定をし、推定相続人の後見申し立てに関する意見書(後見人候補者が後見人になることに関しての同意)を添付することで、裁判所の手続きがスムーズになります。
親族が後見申立てに反対していたり、音信不通であったりなどの事情がある場合、意見書が提出できない事情を上申書等に記載して家庭裁判所に提出します。
ですので、事前に意見書をもらえそうにない親族の有無について、本人や家族等に確認するといいでしょう。
司法書士太田合同事務所からのアドバイス

法定後見の申し立てに必要な書類は、多種多様で作成するのも収集するのも大変なものが多いです。
我々法律専門職でも、後見業務を行う際は時間と手間がかかること多いので、一般の方が行おうとすると尚更でしょう。
またせっかく時間と労力をかけて、申立てをしても親族の方が後見人になれないケースも十分にありますから、そのあたりは専門職に依頼してしまうのもありかと思います。
仮に親族の方が申立てをしないとしても、裁判所に提出する書類のなかに、親族の意見書を提出しますので、そこで後見申立てに関する、自分の率直な意見を述べることもできます。
また後見人は一度付けると、簡単に外すことはできなくなりますので、そのあたりも熟慮したうえで、手続きを行うかご検討ください。
後見のことについて、「認知症対策そうだん窓口」で詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。